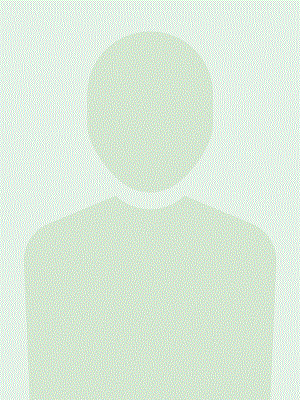論文
|

|
バチカン文庫蔵バレト写本には、宗教などの高度文化構造と言語の基本構成とがどれほど密接に絡み合っているか実感させてくれる日本語による『受難道具問答』が収まっている。聖母マリアとマグダラのマリアとの対話という設定で、鞭、茨の冠、十字架などの聖なる暴力の道具を黙想しながら、交代交代に母性愛と恋愛とを神聖化していく。台詞には日本語能力だけではなく、連歌や能楽で見るような無人称の意識の流れを用いるところで文学的な巧みをも見せているのである。ただし、当時の日本語は人称ではなく敬語で人物を特定するようにできており、同じ存在を目上としても目下としても同時に指示できないので、聖母マリアがイエスを息子としても神の子としても「子」という一言で示すヨーロッパ各国語による受難文学の常套句が不発に終わってしまう。この失敗は、ポルトガル語による端書や大胆な新造句で補充される。一方、マグダラのマリアの性欲の止揚は逐語訳する傾向があって、逆に笑わせることが多い。その後文面が激変して「ごパッションのコトワリ」という付録となり、これは文法や言葉遣いの問題も見られる不自由で事務的な散文で再び受難道具を、今度は茶道具の目録のようにでも「道具」として列挙し、教理正しさを念頭に置いてそれぞれの神学的な作用を網羅する。ここで感じられるのは日本語が(ヨーロッパの)真理を伝えることができるかどうかという(妥当な)不安なのである。 |